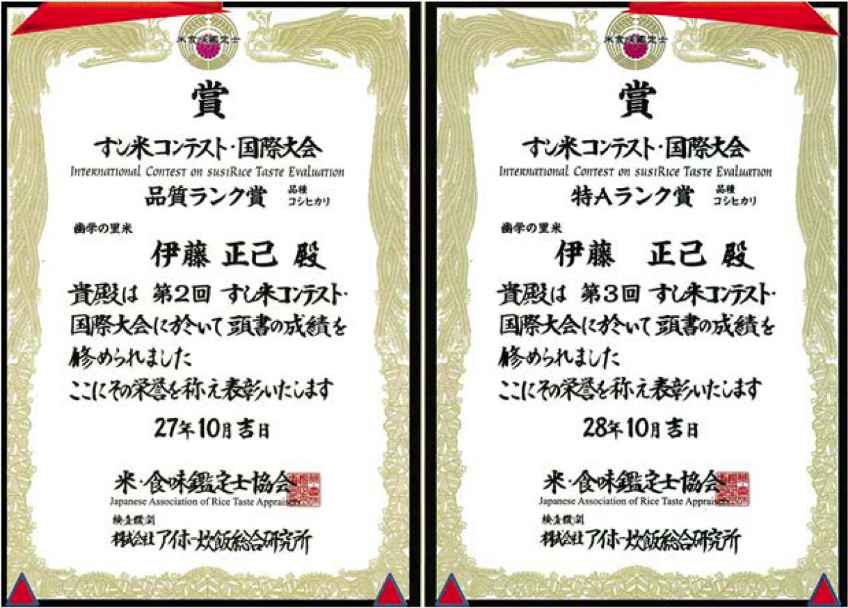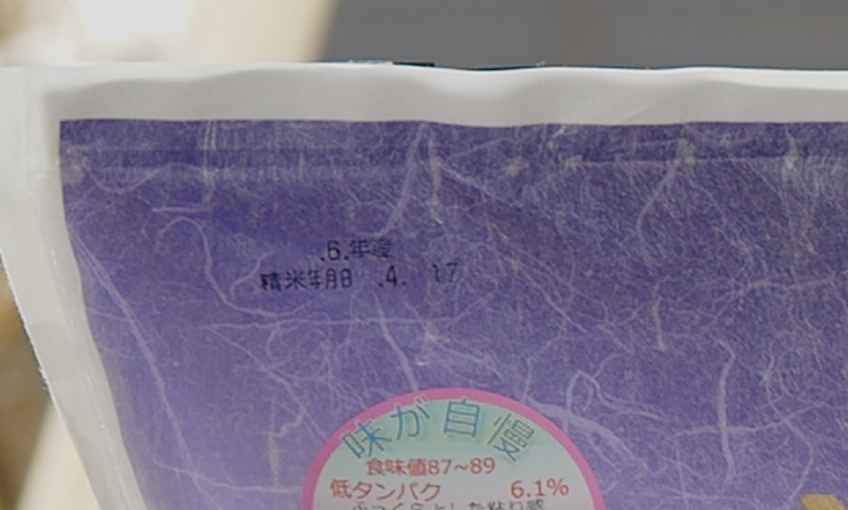「幽学の里米」の名前の由来について教えてください。
「幽学の里米」は、現在の千葉県旭市を中心に房総各地や信州上田などで農民の教化と農村改革運動を指導し、大きな実績を残した大原幽学(1797-1858)から名前を取っています。
大原幽学は、道徳と経済の調和を基本とした「性学(せいがく)」を説き、農民や医師、商家に対して実践的な経営指導を行いました。現在の農業協同組合の原型ともいえる「先祖株組合」を作ったのも大原幽学です。「幽学の里米」には、こうした歴史的背景と地域の誇りが込められています。
大原幽学の教えについては「大原幽学記念館」(千葉県旭市、http://www.city.asahi.chiba.jp/yugaku/)でも詳しく学ぶことができます。